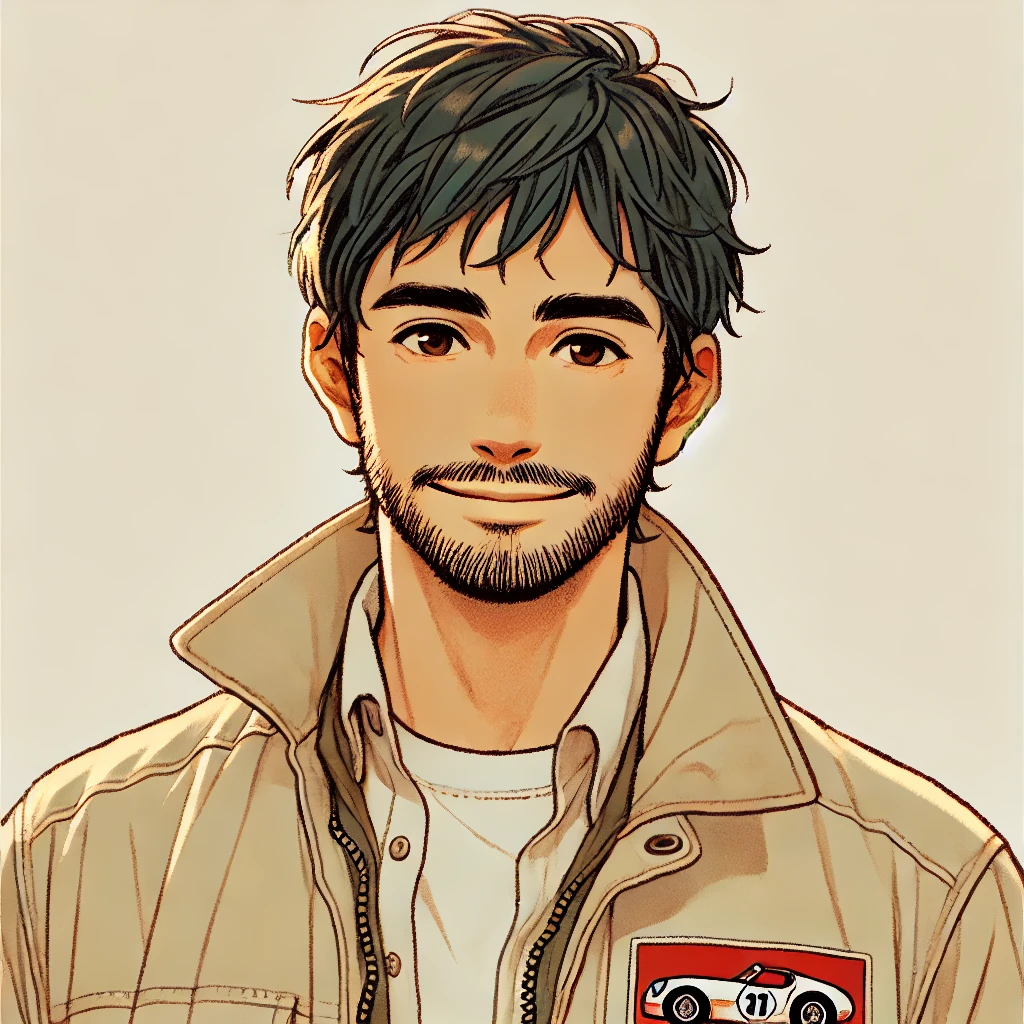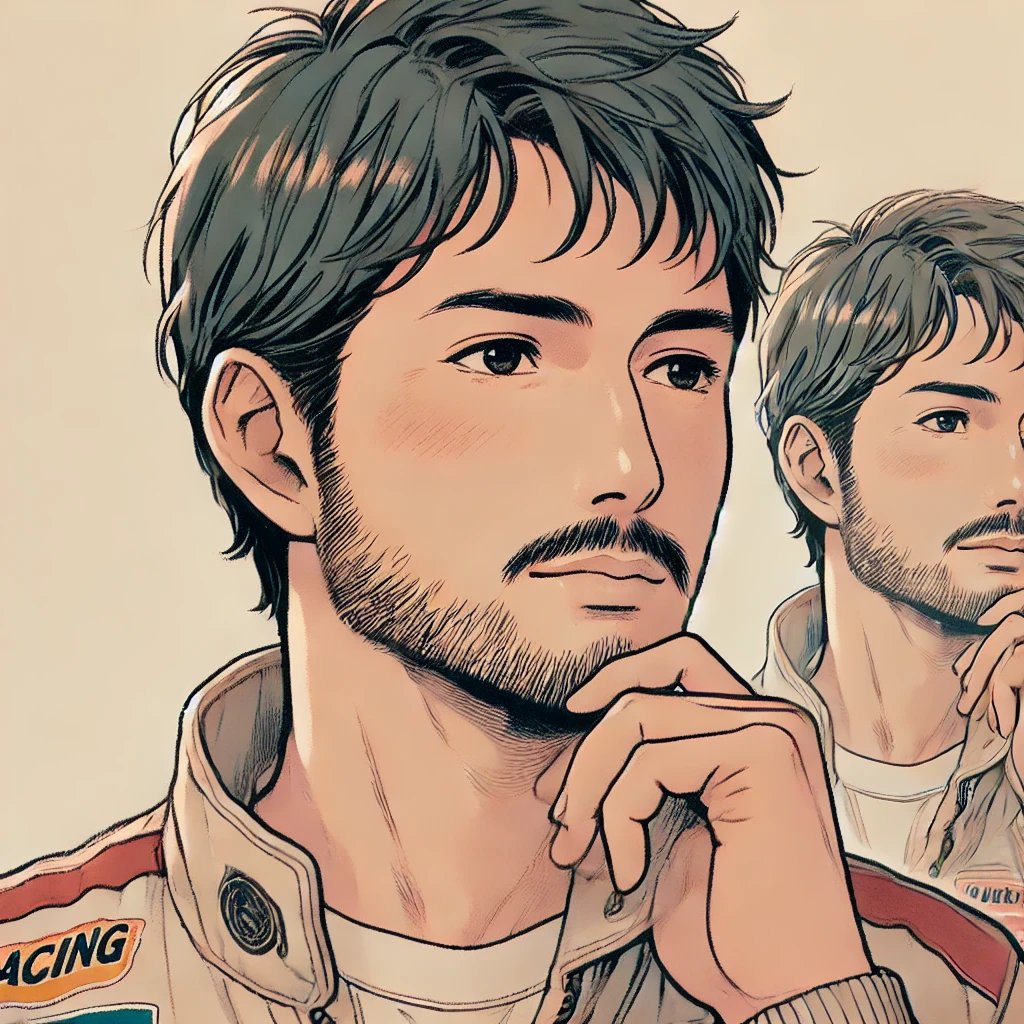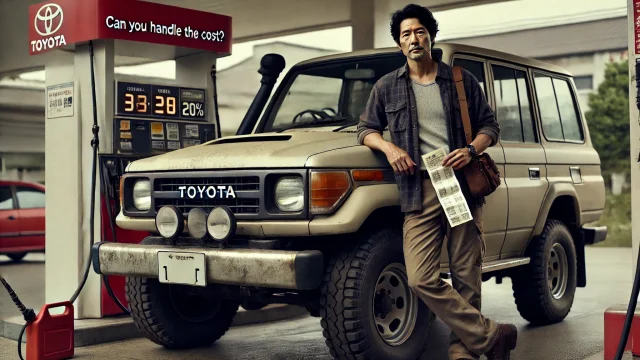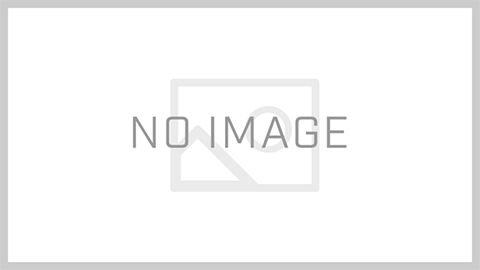日本の自動車史において、特別な地位を築き上げてきたトヨタ センチュリー。皇室の御料車としても採用され、歴代首相をはじめとする政府要人、大企業の役員など、限られた人々を乗せるための最高級ショーファードリブンカーとして、半世紀以上にわたり君臨し続けてきました。
その存在は、単なる移動手段を超え、日本の「おもてなし」の精神と、モノづくりの粋を集めた工芸品とも称されます。街中でセンチュリーを見かける機会は決して多くありませんが、その独特の威厳と風格に、「一体どんな人が乗っているんだろう?」と興味を抱く方もいるのではないでしょうか。
一般のドライバーが気軽に購入できる車ではないだけに、センチュリーのオーナー像は謎に包まれている部分もあります。この記事では、「センチュリーに乗ってる人」に焦点を当て、どのような人々がこの特別な車を選び、所有し、そして利用しているのか、そのリアルな姿に迫ります。
公用車としての役割、企業のトップが選ぶ理由、そして個人の富裕層オーナーの価値観、さらには中古車でセンチュリーの世界に触れる人々まで、様々な角度からオーナー像を紐解いていきます。また、近年登場したSUVタイプの新型センチュリーが、オーナー層にどのような変化をもたらすのかについても考察します。日本の最高級車を取り巻く、特別な世界を覗いてみましょう。
- センチュリーは主に政府要人や大企業役員などのショーファードリブンカーとして利用される
- オーナーは後席の快適性、静粛性、そして車両が持つステータス性や威厳を重視する
- 華美を避けた控えめなデザインも、日本の美意識を反映し選ばれる理由の一つ
- 個人オーナーや、中古車でセンチュリーを楽しむ層も存在するが、限定的
センチュリーに乗るのはどんな人?オーナー像とその背景を探る
- 日本の最高級車 センチュリーという特別な存在
- ショーファードリブンの象徴 運転手付きで後席に乗る人々
- 公用車としてのセンチュリー 皇室・政府・地方自治体での利用
- 大企業の役員や経営者 社用車としての需要
- 個人の富裕層オーナー その価値観と選択の理由
- 新型SUVタイプの登場 オーナー層に変化は?
日本の最高級車 センチュリーという特別な存在
- トヨタブランドの頂点に立つ、日本の最高級乗用車
- 「おもてなし」の精神を体現するショーファードリブンカー
- 熟練した職人の手作業による、工芸品のような作り込み
まずはじめに、トヨタ センチュリーがどのような車なのか、その特別な存在意義を確認しておきましょう。センチュリーは、1967年にトヨタグループの創始者である豊田佐吉の生誕100年を記念して誕生しました。
以来、日本の皇室や政府、企業のトップリーダーなど、国内外のVIPをもてなすための最高級ショーファードリブンカー(運転手が運転し、オーナーは主に後席に乗る車)として、半世紀以上にわたりその地位を守り続けています。
開発コンセプトは「日本の正統フォーマル」。華美な装飾を避け、威厳と品格を湛えた落ち着きのあるデザインと、乗員をもてなすための最高の快適性・静粛性を追求しています。その生産工程も特別で、熟練した「匠」と呼ばれる職人たちが、手作業で多くの工程を担当。
例えば、ボディサイドの美しいキャラクターライン(几帳面と呼ばれる)は、職人の手作業による削り出しで描かれ、象徴である「鳳凰」のエンブレムも手彫りで製作されます。塗装も、複数回の重ね塗りと磨き工程を経て、漆塗りのような深みのある光沢が生み出されます。まさに、単なる工業製品ではなく、日本の伝統技術と美意識が息づく工芸品のような存在なのです。
搭載されるエンジンも特別で、2代目モデル(1997年~2017年)には、国産乗用車としては唯一無二のV型12気筒エンジンが搭載されていました。
このように、センチュリーは、その成り立ちから生産プロセス、そして求められる役割に至るまで、他のどの車とも異なる、日本独自の特別な高級車として存在しているのです。
ショーファードリブンの象徴 運転手付きで後席に乗る人々
- センチュリーは基本的に後席に乗る人のための車
- 広々とした後席空間と、最高の快適性・静粛性が提供される
- オーナーは自ら運転するよりも、移動時間を有効活用することを重視
センチュリーの最も基本的な使われ方であり、その開発思想の根幹にあるのが「ショーファードリブン」、つまり運転手付きで後部座席に乗ることです。
センチュリーに乗っている人の多くは、自らステアリングを握るのではなく、専属の運転手に運転を任せ、後席で過ごす時間を大切にしています。そのため、センチュリーの設計は、何よりも後席の快適性を最優先に考えられています。
広々とした足元空間はもちろん、上質な素材(例えばウールファブリックや本革)で作られたシートは、まるで自宅のソファのようなゆったりとした座り心地を提供します。現行(3代目)セダンモデルでは、左後席に電動オットマンやマッサージ機能なども備わり、まさに移動する執務室、あるいは最高のリラクゼーション空間となっています。
また、徹底した静粛性対策により、車内は外部の騒音から隔離された静かな空間が保たれ、移動中に重要な電話をしたり、書類に目を通したり、あるいは休息を取ったりと、時間を有効に活用することができます。
乗り心地も、路面からの衝撃を極限まで吸収し、常にフラットで穏やかな姿勢を保つようにチューニングされています。
このように、センチュリーに乗る人々は、単に目的地へ移動するだけでなく、その移動時間自体を、快適で有意義なものにしたいと考えているのです。後席での体験こそが、センチュリーの価値の核心であり、オーナーがこの車を選ぶ最大の理由の一つとなっています。
公用車としてのセンチュリー 皇室・政府・地方自治体での利用
- 皇室の御料車(センチュリーロイヤル)として長年使用
- 内閣総理大臣をはじめとする政府高官の専用車としても活躍
- 一部の都道府県知事や企業の公用車としても採用例あり
センチュリーの特別な地位を象徴するのが、「公用車」としての役割です。
日本の象徴である皇室では、天皇皇后両陛下がお乗りになる御料車として、特別仕様の「センチュリーロイヤル」が長年にわたり使用されています。これは、センチュリーが持つ高い信頼性、安全性、そして日本の最高級車としての品格が認められていることの証です。
また、行政府の長である内閣総理大臣の専用車としても、センチュリーが代々採用されてきました。国会への登院や、官邸間の移動、あるいは海外からの賓客を迎える際など、日本のリーダーが公務で使用する車として、センチュリーはその重責を担っています。閣僚や、その他の政府高官の専用車としても、センチュリーが用いられるケースがあります。
さらに、地方自治体に目を向けると、一部の都道府県知事の公用車としてセンチュリーが採用されている例も見られます。これも、その地域の「顔」としての役割を果たす上で、センチュリーの持つ格式が評価されているためでしょう。
これらの公的な役割を担うセンチュリーは、単なる移動手段ではなく、日本の威信や格式を内外に示す象徴としての意味合いも持っています。街中で黒塗りのセンチュリーを見かけた場合、それはもしかしたら、国の重要な役割を担う人物を乗せている公用車かもしれません。
このように、公的な場面で広く採用されている事実が、センチュリーの特別なステータスを揺るぎないものにしているのです。
大企業の役員や経営者 社用車としての需要
- 日本を代表する大企業の社長や会長などの社用車として採用
- 企業の信頼性や格を示す役割も担う
- 取引先への訪問や、重要なゲストの送迎などに使用
公用車と並んで、センチュリーの主要な使われ方の一つが、大企業の「社用車」としての利用です。特に、日本を代表するような大企業の社長、会長、役員といったトップマネジメント層が、日々の移動や、重要なビジネスシーンでセンチュリーを利用しているケースが多く見られます。
企業がセンチュリーを社用車として選ぶ理由は、単に後席の快適性が高いから、というだけではありません。センチュリーが持つ「信頼性」と「品格」が、企業のイメージや信用力にも繋がると考えられているからです。
重要な取引先を訪問する際や、海外からの大切なゲストを送迎する際にセンチュリーを使用することで、相手に対して敬意を示すとともに、自社のステータスや安定性をアピールする効果も期待できます。
また、企業のトップが乗る車として、安全性や信頼性が極めて高いことも重要な要素です。センチュリーは、万が一の事態にも備えた堅牢な作りと、トヨタの最高水準の品質管理によって、高い安全性を確保しています。
さらに、華美になりすぎない、控えめでありながらも威厳のあるデザインが、日本の企業のトップにふさわしいと判断されることも多いようです。ロールスロイスやベントレーといった海外の超高級車とは異なり、センチュリーにはどこか「質実剛健」なイメージがあり、それが日本のビジネスシーンにマッチすると考えられているのかもしれません。
このように、センチュリーは、企業の「顔」としての役割も担う、特別な社用車として、日本のビジネス界で重要な地位を占めているのです。
個人の富裕層オーナー その価値観と選択の理由
- 数は少ないながら、個人でセンチュリーを所有する富裕層も存在する
- 単なるステータスだけでなく、センチュリー独自の価値観に共感
- 日本の伝統や文化、職人技への敬意を持つ人が多い?
センチュリーは主にショーファードリブンカーや公用車・社用車として使われることが多いですが、数は少ないながらも、個人で所有している富裕層のオーナーも存在します。彼らは、なぜ数ある高級車の中からセンチュリーを選ぶのでしょうか?もちろん、センチュリーが持つ高いステータス性や希少性に魅力を感じていることは間違いないでしょう。
しかし、それだけではない、センチュリー独自の価値観に共感しているケースが多いようです。例えば、海外の高級車のような派手さや、最新技術の誇示ではなく、日本の伝統的な美意識に基づいた、控えめでありながらも深い品格を湛えたデザインに惹かれる、という価値観です。
また、熟練した職人の手作業によって生み出される、工芸品のような作り込みや、細部にまで行き届いた「おもてなし」の精神に、日本のモノづくりの粋を感じ、それに価値を見出す人もいるでしょう。
特に、2代目センチュリーに搭載されていたV型12気筒エンジンのような、技術的なこだわりや、他にはない唯一無二の存在であることに魅力を感じる、根っからのクルマ好きという可能性もあります。
個人でセンチュリーを所有する人々は、単に経済的な豊かさを示すだけでなく、日本の文化や伝統、職人技に対する敬意を持ち、センチュリーという車を通じて、そうした価値観を表現しているのかもしれません。
彼らにとってセンチュリーは、単なる移動手段やステータスシンボルを超えた、特別な愛着の対象となっているのではないでしょうか。
新型SUVタイプの登場 オーナー層に変化は?
- 2023年に、従来のセダンに加えてSUVタイプの新型センチュリーが登場
- よりパーソナルな使い方や、自分で運転することも想定したモデル
- 従来のオーナー層に加え、新たな顧客層の獲得も目指す
2023年、センチュリーの歴史に大きな転換点が訪れました。従来の4ドアセダンに加えて、新たにSUVタイプの新型センチュリー(ボディタイプとしてはクロスオーバーに近い)が発表されたのです。
このSUVタイプの登場は、センチュリーのオーナー層に変化をもたらす可能性があるとして注目されています。従来のセンチュリーセダンは、その成り立ちから主に後席に乗ることを前提としたショーファードリブンカーでした。
しかし、新しく登場したSUVタイプは、後席の快適性を高いレベルで維持しつつも、オーナー自らがハンドルを握って運転することも想定した、よりパーソナルなキャラクターが与えられています。
プラグインハイブリッドシステムによる力強い走りや、後輪操舵システムによる取り回しの良さなども、ドライバーズカーとしての側面を強調しています。
この新しいセンチュリーSUVは、従来のセンチュリーの顧客層(政府関係者や企業役員など)に加えて、これまでセンチュリーに興味を持たなかった、より若い世代の富裕層や、アクティブなライフスタイルを送る人々など、新たな顧客層へのアピールも狙っていると考えられます。
例えば、自分で運転して別荘に行ったり、家族とレジャーに出かけたり、といった使い方にも対応できる、より多用途なセンチュリー像を提示しています。もちろん、SUVタイプであっても、センチュリーとしての威厳や格式、そして「おもてなし」の精神は継承されています。
今後、この新しいSUVタイプが市場にどのように受け入れられ、センチュリーのオーナー像がどのように変化していくのか、非常に興味深いところです。伝統と革新が融合した新しいセンチュリーの展開から目が離せません。
ショーファードリブンから個人オーナーまで センチュリーの多様な使われ方
- 後席の快適性を最優先 おもてなしのための空間
- ステータスと威厳の象徴 社会的な地位を示す役割
- 控えめなデザインの魅力 華美を避ける日本の美意識
- 中古車でセンチュリーを楽しむ人々 その魅力と維持
- 伝説のV12エンジン搭載モデル(2代目)への憧れ
- センチュリーオーナーに共通する価値観とは?
- まとめ:センチュリーを選ぶということ その意味と覚悟
後席の快適性を最優先 おもてなしのための空間
- センチュリーの本質は、後席に乗る人のための最高の快適性
- 広々とした空間、上質なシート、卓越した静粛性
- 移動時間を最高のリラックスタイムまたは執務時間に変える
センチュリーがセンチュリーたる所以、その本質は、やはり後部座席にあります。この車は、運転する人のためではなく、後席に乗る人に最高の快適性と「おもてなし」を提供するために作られています。ドアを開けた瞬間から、その特別な空間は始まります。
足元にはふかふかのフロアマットが敷かれ、シートには厳選されたウールファブリックや最高級の本革が使用されています。シートに腰を下ろせば、まるで高級なソファのような、ゆったりとしたサイズと、体を優しく包み込むような絶妙なクッション性が感じられます。
足元スペースは広大で、足を伸ばしてくつろぐことができます。現行セダンの左後席には電動オットマンも備わり、まさにファーストクラスのような快適さです。
そして、走り出せば、その卓越した静粛性に驚かされるでしょう。エンジン音やロードノイズは徹底的に遮断され、車内はまるで外界から隔離されたかのような静寂に包まれます。
これにより、移動中に仮眠をとったり、集中して仕事を進めたり、あるいは同乗者と気兼ねなく会話を楽しんだりすることが可能です。乗り心地も、あくまで後席の快適性を最優先にチューニングされており、路面からの衝撃は極限まで抑えられ、常に穏やかでフラットな姿勢を保ちます。
センチュリーの後席は、単なる移動のための座席ではなく、乗る人をもてなし、最高のリラックスタイム、あるいは集中できる執務空間を提供する、特別な場所なのです。
ステータスと威厳の象徴 社会的な地位を示す役割
- センチュリーに乗ることは、高い社会的地位や成功の証と見なされる
- 多くを語らずとも、その存在感が周囲に影響を与える
- ビジネスシーンなどにおいて、信頼感や格を示す効果も
センチュリーは、その成り立ちや使われ方から、単なる高級車というだけでなく、高い「ステータスシンボル」としての側面も持っています。
センチュリーに乗っている、あるいはセンチュリーで送迎されるということは、その人が社会的に高い地位にあることや、経済的に成功していることの証として、周囲から認識される傾向があります。
多くを語らずとも、センチュリーという車が持つ独特の威厳とオーラが、そのオーナーや乗員の社会的地位を雄弁に物語るのです。これは、特にビジネスシーンにおいて、有利に働く場合があります。
例えば、重要な商談相手をセンチュリーで迎えに行けば、相手に対して最大限の敬意を示すと同時に、自社の信頼性や格の高さを暗に示すことができます。
また、企業のトップがセンチュリーに乗ることで、従業員や株主に対して、会社の安定性や将来性といったメッセージを発信する効果も期待できるかもしれません。もちろん、現代においては、ステータスを誇示することだけが価値ではありません。
しかし、日本の社会において、センチュリーが長年培ってきた「特別な車」というイメージは依然として強く、その存在感が持つ影響力は無視できません。
センチュリーを選ぶ人々の中には、後席の快適性だけでなく、この車が持つステータス性や、社会的な信用力を意識している人も少なくないでしょう。センチュリーは、乗る人の「格」をも高める、そんな特別な力を持った車なのです。
控えめなデザインの魅力 華美を避ける日本の美意識
- 派手さや豪華さを前面に出さず、奥ゆかしさと品格を重視
- 日本の伝統的な美意識「わび・さび」にも通じるデザイン
- 長く乗っても飽きない、普遍的な魅力を持つ
センチュリーのデザインは、一見すると非常にシンプルで、他の高級車のような派手さはありません。しかし、その控えめなデザインこそが、センチュリーの大きな魅力であり、多くの人々(特に日本の要人や経営者)に選ばれる理由の一つとなっています。
センチュリーのデザインは、過度な装飾や、流行のデザイン要素を追うことをせず、日本の伝統的な美意識に基づいた、普遍的で飽きのこない造形を追求しています。
例えば、ボディサイドを貫く「几帳面」と呼ばれるキャラクターラインは、平安時代の屏風などの柱の面取りから着想を得たものであり、凛とした品格を表現しています。フロントグリルやエンブレムに使われる「鳳凰」のモチーフも、日本の伝統的な吉祥文様です。
全体として、華美を避け、質実剛健でありながらも、細部にまで神経の行き届いた、奥ゆかしい美しさを湛えています。これは、自己主張の強い海外の高級車とは一線を画す、日本独自の価値観と言えるでしょう。
この控えめなデザインは、「能ある鷹は爪を隠す」という日本のことわざにも通じるように、真の実力や品格は、声高に主張せずとも滲み出るものである、という考え方を体現しているのかもしれません。
また、流行に左右されないデザインは、何十年という長い年月を経ても古さを感じさせず、長く乗り続けることができるというメリットもあります。センチュリーを選ぶ人々は、この奥ゆかしいデザインの中に、真の豊かさや日本の美意識を見出しているのではないでしょうか。
中古車でセンチュリーを楽しむ人々 その魅力と維持
- 中古車なら、憧れのセンチュリーを比較的安価に入手可能
- 独特の乗り味や雰囲気を、個人オーナーとして楽しむ
- ただし、維持費(特にV12モデル)は高額になる覚悟が必要
新車ではなかなか手の届かないセンチュリーですが、中古車市場に目を向けると、年式や走行距離によっては、驚くほど手頃な価格で販売されている個体を見つけることができます。これにより、これまで縁がなかったような一般の自動車ファンでも、センチュリーのオーナーになるという夢を叶えることが可能になります。
中古でセンチュリーを購入する人々は、その独特の世界観や魅力に惹かれている場合が多いようです。
例えば、国産唯一のV12エンジン(2代目モデル)の滑らかなフィーリングや、他のどの車とも違う、重厚で静かな乗り心地、そして威風堂々とした佇まいなどに魅力を感じ、個人で所有して楽しみたいと考えているのです。
自分で運転するも良し、たまには友人に運転してもらって後席のVIP気分を味わうも良し、様々な楽しみ方ができます。
ただし、中古でセンチュリーを所有するには、相応の覚悟も必要です。特に注意が必要なのが「維持費」です。車両価格が安くても、元々は最高級車。部品代は非常に高価で、整備にも専門的な知識や技術が求められます。
特に、V12エンジン搭載の2代目モデルは、燃費が悪く、自動車税も高額で、万が一エンジンにトラブルが発生した場合の修理費用は莫大なものになる可能性があります。オイル交換やタイヤ交換といった基本的なメンテナンスだけでも、一般的な車種より費用がかさみます。
中古センチュリーは、購入価格だけでなく、その後の維持費もしっかりと計画し、ある程度の知識と情熱を持って付き合っていく必要がある、趣味性の高い選択と言えるでしょう。安易な気持ちで手を出すのは危険かもしれません。
伝説のV12エンジン搭載モデル(2代目)への憧れ
- 国産乗用車唯一のV12エンジンを搭載した2代目センチュリー
- その滑らかさ、静粛性、希少性から、今なお高い人気を誇る
- 中古車市場でも、状態の良い個体は高値で取引されることも
センチュリーの歴史の中でも、特に自動車ファンの間で伝説として語り継がれているのが、1997年から2017年まで生産された2代目モデルです。その最大の理由は、国産乗用車としては唯一無二となる、5.0L V型12気筒エンジン(1GZ-FE型)を搭載していたことにあります。
V12エンジンは、その構造上、振動が極めて少なく、非常に滑らかで静かな回転フィールを実現できるとされています。センチュリーに搭載されたV12エンジンも、まさに絹のように滑らかで、どこまでも静かに回る、極上のフィーリングを提供しました。
最高出力自体は当時の自主規制値に合わせて抑えられていましたが、その存在意義はパワーではなく、あくまで最高級車にふさわしい滑らかさと静粛性の追求にありました。
このV12エンジン搭載のセンチュリーは、その希少性と独特の魅力から、生産が終了した現在でも、中古車市場で根強い人気を誇っています。特に、走行距離が少なく、内外装の状態が良い個体や、最終型に近いモデルなどは、年式が古くても比較的高値で取引される傾向があります。
多くの自動車ファンにとって、このV12センチュリーは一度は所有してみたい、あるいは運転してみたい憧れの存在なのです。もちろん、前述の通り、V12エンジンならではの維持費の高さ(燃費、税金、整備費)という大きなハードルは存在します。
しかし、それを乗り越えてでも所有したいと思わせるだけの、特別な魅力とロマンが、この2代目センチュリーには詰まっていると言えるでしょう。日本の自動車史に残る名車の一つです。
センチュリーオーナーに共通する価値観とは?
- 単なる移動手段としてではなく、車に特別な価値を見出している
- ステータス、快適性、伝統、日本の美意識などを重視
- 流行に左右されず、本質的な価値を理解し、長く大切にする傾向
公用車、社用車、そして個人の愛車として、様々な形で選ばれるセンチュリー。そのオーナーたちには、いくつかの共通する価値観があるように思われます。まず、彼らは車を単なる「移動手段」として捉えていない、ということです。
センチュリーが提供する、移動時間そのものの質(快適性、静粛性)、あるいはセンチュリーが持つ社会的意味合い(ステータス、威厳)、さらにはその背景にある歴史や文化といった、目に見える機能や性能だけではない、より深い価値を重視していると言えるでしょう。
また、彼らは「本質」を見抜く目を持っているのかもしれません。センチュリーは、最新の流行デザインや、派手なパフォーマンスを追い求める車ではありません。むしろ、時代が変わっても色褪せない普遍的なデザインや、過剰な機能ではなく本当に必要な「おもてなし」の装備、そして長年にわたって培われてきた信頼性といった、本質的な価値を提供しています。
センチュリーを選ぶ人々は、こうした本質的な価値を理解し、それに共感しているのではないでしょうか。そして、一度選んだものを「長く大切にする」という価値観も共通しているかもしれません。
センチュリーは、頻繁にモデルチェンジを繰り返す車ではありません。オーナーもまた、流行に流されることなく、一台のセンチュリーと長く、深く付き合っていく傾向があるように思われます。それは、車に対する愛着だけでなく、日本の伝統や文化を尊重する姿勢の表れとも言えるかもしれません。
これらの価値観を持つ人々にとって、センチュリーは唯一無二の、特別なパートナーとなっているのです。
まとめ:センチュリーを選ぶということ その意味と覚悟
- センチュリーに乗る人は、主に政府要人、企業役員、一部の富裕層など限られた人々。
- 多くはショーファードリブンとして、後席の快適性やステータス性を重視して利用される。
- 公用車・社用車としての役割も大きく、日本の威信や企業の格を示す象徴でもある。
- 個人オーナーは、単なる富の象徴としてではなく、センチュリー独自の価値観(日本の美意識、職人技など)に共感している。
- 控えめながらも品格のあるデザイン、卓越した静粛性と乗り心地が、世代を超えて評価される。
- 中古車でセンチュリーを楽しむ層も存在するが、維持費(特にV12モデル)への覚悟が必要。
- 2代目モデルのV12エンジンは、今なお多くのファンを魅了する伝説的な存在。
- 近年登場したSUVタイプは、新たなオーナー層を開拓する可能性を秘めている。
- センチュリーを選ぶことは、単に車を選ぶだけでなく、特別な価値観やライフスタイルを選ぶことを意味する。
- 流行に左右されず、本質を理解し、長く大切にする姿勢が求められる、特別な車。
こんにちは、いつかはセンチュリーの後席に乗ってみたい…と密かに夢見る運営者です!今回も、日本の最高級車という、少し特別なテーマの記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます!
センチュリーって、本当に独特なオーラがありますよね。街で見かけると、「おっ!」っと思って、思わず目で追ってしまいます。そして、「どんな人が乗ってるんだろう?」って、やっぱり考えちゃいます。
この記事を書いてみて、センチュリーに乗っている方々が、単にお金持ちというだけでなく、車に対して、あるいは日本の文化やモノづくりに対して、深い理解と敬意を持っていることが多いんだろうな、と感じました。派手さよりも品格を、最新技術のひけらかしよりも本質的な快適性を求める、そんな成熟した価値観をお持ちの方が多いのかもしれません。
もちろん、公用車や社用車としての役割が大きい車ですが、個人で所有されている方や、中古で憧れのセンチュリーを手に入れて大切に乗られている方もいらっしゃる。特にV12エンジン搭載の2代目なんて、もうロマンの塊ですよね!維持するのは本当に大変そうですが…。
最近はSUVタイプも登場して、これからセンチュリーのオーナー像も少しずつ変わっていくのかもしれません。自分で運転するセンチュリー、というのも、また新しい魅力がありそうです。
もしあなたが将来、何らかの形でセンチュリーに関わる機会があったなら、この記事で触れたような、センチュリーが持つ特別な背景や価値観を少し思い出していただけると嬉しいです。それはきっと、単なる移動体験を超えた、何かを感じさせてくれるはずですから。
日本の誇る最高級車センチュリー。その特別な世界に、少しでも触れるお手伝いができたなら幸いです。ありがとうございました!