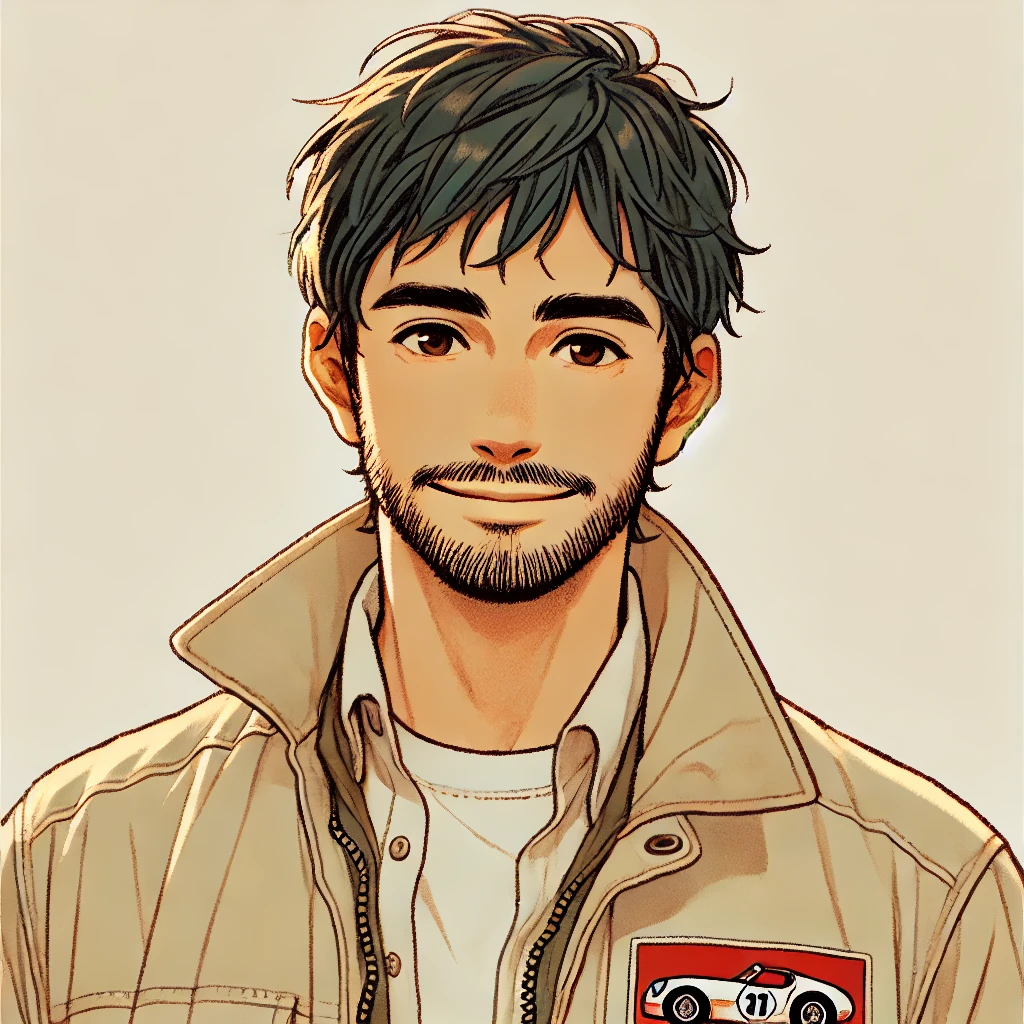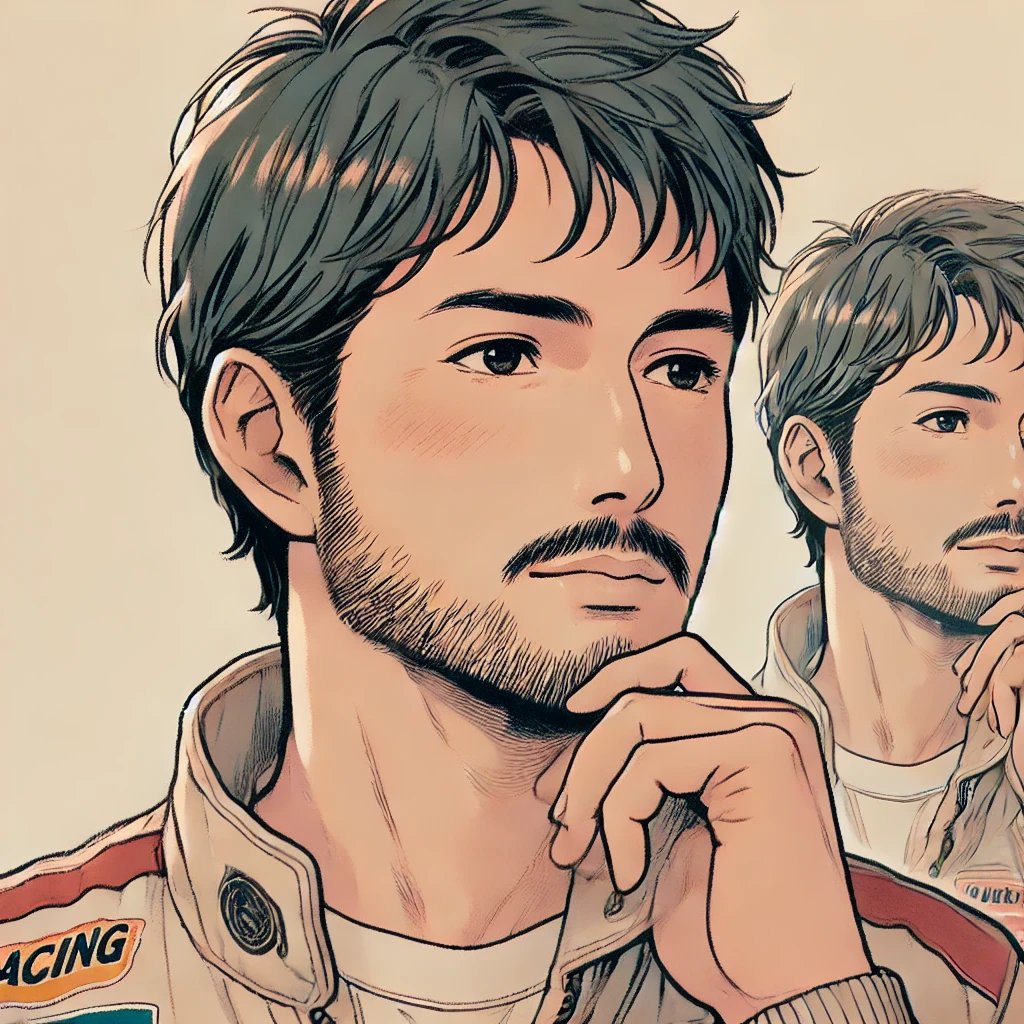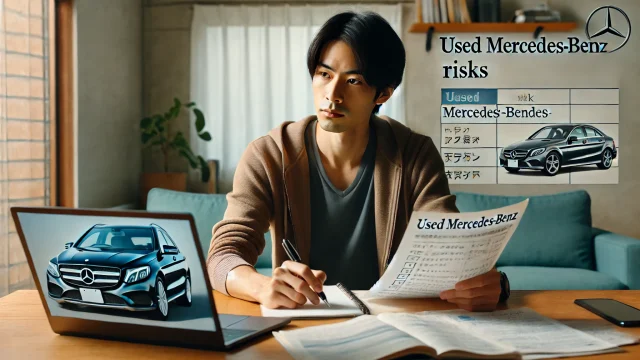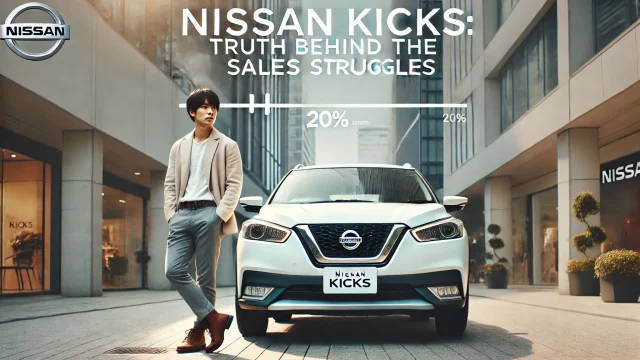マツダの新世代ラージ商品群の第一弾として鳴り物入りで登場したCX-60。縦置きFRプラットフォームを採用し、直列6気筒ディーゼルエンジンやPHEVといった新しいパワートレイン、そしてマツダらしい洗練されたデザインと高級感あふれる内装で大きな注目を集めました。
しかし、発売から時間が経つにつれて、インターネットのクチコミや掲示板、SNSなどでは「CX-60 やばい」というキーワードが目立つようになりました。これは一体どういうことなのでしょうか?単なる噂なのか、それとも本当に購入をためらうべき「やばい」問題を抱えているのでしょうか?
この「やばい」という言葉には、実はポジティブな意味とネガティブな意味の両方が含まれているようです。デザインや走り、高級感に対して「やばい(=すごい、素晴らしい)」という称賛の声がある一方で、特に初期型モデルを中心に、乗り心地の硬さ、新開発の8速ATミッションのギクシャク感、頻発する不具合やリコール情報など、ネガティブな意味で「やばい(=問題が多い、ひどい)」という声が挙がっているのも事実です。
特にディーゼルエンジンモデルの乗り心地やミッション制御に関するトラブルの書き込みは多く、購入を検討しているユーザーにとっては大きな不安要素となっています。
このページでは、マツダCX-60の「やばい」と言われる様々な側面を、ユーザーのリアルなクチコミやレビュー、公開されている情報などを元に徹底的に深掘りします。ネガティブな評判である不具合やリコール、乗り心地の問題点とその改善・対策状況、ディーラーの対応、中古車選びの注意点などを詳しく解説。
さらに、デザインや内装の魅力、FRならではの走り、燃費性能といったポジティブな側面や、ライバルとなるCX-5との比較なども交えながら、CX-60の実像に迫ります。この記事を読めば、CX-60が本当に「やばい」のか、そしてあなたが購入を検討すべき車種なのか、客観的な判断ができるようになるはずです。支払総額や保証、整備に関する情報も踏まえ、後悔しないクルマ選びをサポートします。
- CX-60が「やばい」と言われるポジティブ・ネガティブ両面の理由
- 初期型に多かった不具合、リコール情報とその後の改善状況
- 乗り心地やミッションのギクシャク感に関するユーザーレビューと対策
- デザイン、内装、走りなどCX-60ならではの魅力と評価
CX-60の「やばい」評判?ネガティブな側面を徹底検証
- CX-60の「やばい」評判の真相は?クチコミ・掲示板の声を分析
- 多発する不具合とリコール情報!初期型オーナーの悩みと対策
- 乗り心地が硬すぎる?CX-60のサスペンション問題を徹底検証
- ギクシャク?異音?CX-60 8速ATミッションのトラブルと評価
- ディーラーの対応はどう?CX-60の不具合に対するメーカー保証と整備体制
- CX-60 ディーゼルエンジンは本当に「やばい」のか?煤問題や燃費を検証
- 初期型と改良後の違いは?中古車購入時の注意点
CX-60の「やばい」評判の真相は?クチコミ・掲示板の声を分析
- ネット上では「乗り心地が悪い」「ミッションがギクシャクする」等のネガティブな声が目立つ
- 一方で「デザインが良い」「走りが楽しい」といったポジティブな評価も多数存在する
- 初期型モデルに対する不満が多く、改良によって改善されている部分もある
マツダCX-60について調べ始めると、インターネット上のクチコミサイトや自動車掲示板、SNSなどで「やばい」という言葉を頻繁に目にします。この言葉が、良い意味なのか悪い意味なのか、非常に気になるところですよね。実際のところ、CX-60に対する評価は、称賛と批判の両方が混在しており、まさに「賛否両論」といった状況です。購入後に後悔しないためには、これらの様々な声を客観的に分析し、「やばい」と言われる真相を探る必要があります。
まず、ネガティブな意味で「やばい」と言われる主な理由を探ってみましょう。最も多く指摘されているのが、「乗り心地の悪さ」です。特に初期型モデルのディーゼル車において、「サスペンションが硬すぎる」「路面の凹凸を拾いすぎて不快」「後部座席は特に突き上げがひどい」といった声が多数挙がっています。これは、新開発のプラットフォームやサスペンションセッティングに起因するものと考えられており、多くのユーザーが不満を感じているポイントです。
次に多く聞かれるのが、「8速ATミッションの制御」に関する問題です。具体的には、「低速域でのギクシャク感」「変速ショックが大きい」「異音が発生する」といった不具合の報告が相次ぎました。新開発のトルクコンバーターレス8速ATは、ダイレクト感のある走りを追求した一方で、特に発売初期の制御プログラムに課題を抱えていたようです。
これらの乗り心地やミッションの問題は、ユーザーの期待が大きかっただけに、失望の声も大きくなり、「やばい」という評価に繋がったと考えられます。さらに、細かな電子制御系の不具合や、リコールが複数回発生したことも、ネガティブなイメージを助長しました。掲示板などでは、具体的なトラブル内容やディーラーとのやり取りなどが詳細に書き込みされており、これから購入を検討する人にとっては不安材料となっています。
一方で、ポジティブな意味で「やばい」と評価されている点も多くあります。まず挙げられるのが、そのエクステリアデザインです。マツダのデザインテーマ「魂動(こどう)」を深化させ、FRらしいロングノーズ・ショートデッキのプロポーションと、力強くもエレガントな造形は、「国産SUVとは思えないほど美しい」「存在感がやばい」と高く評価されています。
インテリアも同様で、上質な素材をふんだんに使用し、細部の仕上げにもこだわった高級感あふれる空間は、「欧州プレミアムSUVに匹敵する」「内装の質感がやばい」と絶賛されています。特に上位グレードのタンカラー内装などは、その美しさが際立っています。また、FRプラットフォームと直列6気筒エンジン(特にディーゼル)がもたらす「走り」についても、「FRらしい素直なハンドリングが楽しい」「ディーゼルのトルク感がやばい」「高速道路での安定性が素晴らしい」といった称賛の声が多く聞かれます。
このように、CX-60の「やばい」評判は、一面的なものではありません。特に初期型モデルで指摘されたネガティブな部分は、その後の年次改良やソフトウェアアップデートで改善が進んでいるという情報もあります。クチコミや掲示板の声は参考になりますが、鵜呑みにせず、可能であれば試乗などを通じて自身の感覚で評価することが重要です。
多発する不具合とリコール情報!初期型オーナーの悩みと対策
- 発売初期を中心に、ミッション制御や電子系統の不具合報告が相次いだ
- 複数回のリコールが実施され、対象車両は無償での部品交換やプログラム修正が必要
- 不具合に対するディーラーの対応やメーカー保証の活用が重要になる
マツダCX-60が「やばい」と言われる大きな要因の一つに、発売初期から報告されている様々な不具合や、それに伴うリコールの実施があります。特に初期型(主に2022年後半から2023年初頭にかけて生産されたモデル)のオーナーからは、多くの悩みや不安の声が聞かれました。これからCX-60の購入を検討している方、特に中古車を視野に入れている方は、これらの情報をしっかりと把握しておく必要があります。
まず、具体的にどのような不具合が報告されていたのでしょうか。最も多かったのは、前述の通り「8速ATミッション」に関するものです。低速走行時のギクシャク感、変速ショック、異音、特定の条件下での変速不良などが代表的な症状として挙げられています。これは、新開発のトルクコンバーターレス構造と制御プログラムのマッチングが、発売当初は十分でなかったことが原因と考えられます。
次に多かったのが、乗り心地に関する問題、特にリアサスペンションの硬さによる突き上げ感です。これも新設計のプラットフォームとサスペンションに関連する問題で、多くの初期型オーナーが改善を求めていました。さらに、電子制御システムに関する不具合も複数報告されています。
例えば、マツダコネクト(ナビゲーションやインフォテインメントシステム)のフリーズや再起動、各種センサーのエラー表示、パワーリフトゲートの作動不良など、内容は多岐にわたります。これらの不具合は、走行に直接的な危険を及ぼすものは少ないものの、日常的な使用におけるストレスや不安感につながり、「やばい」という評価を生む一因となりました。
これらの不具合に対し、マツダは複数回のリコールやサービスキャンペーンを実施しています。例えば、8速ATの制御プログラムのアップデート、エンジン制御コンピュータのプログラム修正、パーキングブレーキ制御プログラムの修正などが行われました。リコールの対象となった車両のオーナーには、ディーラーから連絡があり、無償での点検・部品交換・プログラム修正が実施されます。
中古車で購入した場合でも、リコール対象であれば同様に対応してもらえます。車台番号がリコールの対象となっているか否かは、マツダの公式サイトで確認することができます。しかし、リコール対応後も完全に不具合が解消されなかったり、別の問題が発生したりするケースも一部で報告されており、オーナーの悩みが完全に解消されたとは言えない状況も見受けられます。不具合が発生した場合、まずは購入したディーラーに相談することが基本となります。
メーカー保証期間内(通常は新車登録から3年間または走行距離6万km、特別保証部品は5年間または10万km)であれば、無償で修理を受けられる可能性が高いです。ディーラーの対応に不満がある場合は、マツダのカスタマーセンターに相談することも可能です。初期型CX-60の中古車を検討する際は、これらの不具合やリコールの履歴、対策がきちんと施されているかを確認することが非常に重要です。可能であれば、改良が進んだ後のモデル(年次改良後)を選ぶ方が、トラブルに遭遇するリスクは低いと言えるでしょう。
乗り心地が硬すぎる?CX-60のサスペンション問題を徹底検証
- 特に初期型のリアサスペンションが硬く、突き上げ感が強いとの評価が多い
- 新開発FRプラットフォームとサスペンション形式が影響している可能性
- 年次改良でダンパー等の見直しが行われ、乗り心地は改善傾向にある
CX-60の「やばい」と言われる評判の中でも、特に多くのユーザーから指摘されているのが「乗り心地の硬さ」です。特にリアサスペンションからの突き上げ感が強いという声が多く、同乗者、特に後部座席に乗る人からは不満が出やすいポイントとなっています。「ゴツゴツする」「跳ねる感じがする」「長距離だと疲れる」といったクチコミやレビューが、インターネット上に数多く見られます。なぜCX-60の乗り心地は硬いと言われるのでしょうか?そして、その問題は現在改善されているのでしょうか?詳しく検証してみましょう。
まず、乗り心地が硬いと感じられる原因として考えられるのが、CX-60が採用する新しいプラットフォームとサスペンション形式です。CX-60は、マツダが新開発した縦置きエンジンFR(後輪駆動)ベースのプラットフォームを採用しています。これは、走行性能、特にハンドリング性能を重視した設計思想の表れです。サスペンション形式は、フロントがダブルウィッシュボーン式、リアがマルチリンク式と、形式自体は一般的ですが、そのセッティングが影響している可能性があります。
特に問題視されているリアサスペンションについては、初期型モデルではダンパーの減衰力設定などが、日本の道路環境やユーザーの感覚と必ずしもマッチしていなかったのではないか、という指摘があります。マツダとしては、FRプラットフォームのポテンシャルを活かし、スポーティでダイレクト感のあるハンドリングを実現するために、ある程度引き締まった足回りを目指したのかもしれません。
しかし、その結果として、路面の細かな凹凸や段差を乗り越える際の衝撃が吸収しきれず、ゴツゴツとした硬さや突き上げ感として乗員に伝わってしまったと考えられます。特に、車両重量のあるディーゼルモデルやPHEVモデルで、その傾向が顕著に感じられたようです。また、ランフラットタイヤを装着しているモデル(一部グレード)では、タイヤ自体の硬さも乗り心地に影響を与えている可能性があります。
この乗り心地の問題に対して、マツダも認識しており、年次改良によって改善を図っています。具体的には、2023年後半以降の改良モデルでは、リアダンパーの特性が見直され、よりしなやかな動きをするように変更されたと言われています。実際に改良後のモデルに試乗したユーザーや自動車評論家からは、「初期型に比べて明らかに突き上げ感が減った」「乗り心地がマイルドになった」といった肯定的な評価が出てきています。
ソフトウェアアップデートによる制御(G-ベクタリングコントロールなど)の最適化も、乗り心地改善に寄与している可能性があります。ただし、乗り心地の感じ方は個人の好みや感覚に大きく左右されるため、改良後モデルであっても「まだ硬い」と感じる人もいるかもしれません。CX-60の購入を検討する際には、グレードや年式による乗り心地の違いを意識し、必ず実際に試乗して、様々な路面状況で乗り心地を確認することをお勧めします。特に後部座席の乗り心地もチェックしておくと、家族や友人を乗せる際に後悔することが少なくなるでしょう。もし中古車を検討する場合は、初期型か改良後モデルかを確認し、可能であれば乗り比べてみるのがベストです。
ギクシャク?異音?CX-60 8速ATミッションのトラブルと評価
- 新開発のトルクコンバーターレス8速ATで、低速時のギクシャク感や変速ショックが多発
- 異音や特定の操作での変速不良といったトラブル報告も
- ソフトウェアアップデートで制御は改善されているが、根本的な解決に至らないケースも
乗り心地と並んで、CX-60が「やばい」と言われる原因となっているのが、新開発された8速オートマチックトランスミッション(8AT)に関するトラブルです。マツダはこの新しいミッションを、ダイレクト感のある走りと優れた燃費性能を両立させるために開発しましたが、特に発売初期のモデルにおいて、その制御に関する問題が多く報告されました。「低速でギクシャクする」「変速ショックが大きい」「発進時にもたつく」「走行中に異音がする」といった不満の声が、オーナーや試乗したユーザーから多数挙がっています。
このミッションの問題は、CX-60の評価に大きな影響を与えています。なぜこのようなトラブルが発生し、現在はどうなっているのでしょうか?詳しく見ていきましょう。CX-60に搭載されている8速ATは、一般的なATで使われているトルクコンバーター(トルコン)の代わりに、湿式多板クラッチを使用しているのが大きな特徴です。
トルコンは滑らかな発進や変速に貢献する一方、構造上どうしても動力伝達のロスが発生します。マツダは、このトルコンをなくし、クラッチで直接動力を繋ぐことで、MT(マニュアルトランスミッション)のようなダイレクトなフィーリングと、伝達効率の向上(=燃費向上)を狙いました。
しかし、この新しい構造と、それを制御するソフトウェアの熟成が、発売当初は十分でなかったと考えられます。特に、クラッチの断続制御がうまくいかず、発進時や低速走行時、あるいは加減速を繰り返すような場面で、ギクシャクとした挙動や不快な変速ショックが発生してしまったようです。また、特定の条件下で異音が発生したり、意図した通りに変速しなかったりといった不具合も報告されています。
これらの症状は、ドライバーにとって大きなストレスとなり、CX-60の売りの一つであったはずの「走りの質感」を損なう結果となりました。特に、ストップ&ゴーの多い日本の交通環境では、この低速域でのギクシャク感が目立ちやすかったのかもしれません。
マツダはこの問題に対し、複数回のソフトウェアアップデートを実施することで対応しています。制御プログラムを改良し、クラッチの繋ぎ方や変速タイミングを最適化することで、ギクシャク感や変速ショックの低減を図っています。実際にアップデートを受けたユーザーからは、「かなりスムーズになった」「以前のようなギクシャク感はほぼ感じなくなった」といった改善報告も多く聞かれます。
しかし、全ての車両で完全に問題が解消されたわけではなく、アップデート後も依然として症状が残っている、あるいは別の問題(例えば、燃費の若干の悪化など)を感じるという声も一部にはあります。また、ハードウェア(ミッション本体やクラッチ部品)に起因する問題であった場合は、ソフトウェアアップデートだけでは根本的な解決に至らない可能性も考えられます。ミッションのフィーリングは、乗り心地と同様に個人の感覚差が大きい部分でもあります。
購入を検討する際は、必ず試乗し、特に低速域での走行フィールや変速のスムーズさを入念にチェックすることをお勧めします。可能であれば、初期型と改良後のモデルを乗り比べることで、改善の度合いを確認するのも良いでしょう。中古車を選ぶ際にも、ミッションに関する不具合履歴やリコール対応状況を確認することが重要です。
ディーラーの対応はどう?CX-60の不具合に対するメーカー保証と整備体制
- 不具合発生時のディーラー対応には、店舗や担当者によって差があるとの声も
- メーカー保証(新車保証)を活用し、期間内であれば無償修理が可能
- リコールやサービスキャンペーンの情報は、公式サイト等で確認できる
CX-60で乗り心地やミッションの不具合、その他のトラブルに遭遇した場合、頼りになるのが購入したマツダディーラーの存在です。しかし、インターネット上のクチコミなどを見ていると、ディーラーの対応についても様々な声が聞かれます。「親身になって相談に乗ってくれた」「迅速に対応してくれた」というポジティブな評価がある一方で、「なかなか不具合を認めてくれない」「対応が遅い」「説明が不十分」といったネガティブな意見も見受けられます。
不具合発生時に適切な対応を受けられるかどうかは、オーナーにとって非常に重要な問題です。ここでは、CX-60の不具合に対するディーラーの対応や、メーカー保証、整備体制について解説します。まず、ディーラーの対応に差が出ると言われる背景には、いくつかの要因が考えられます。CX-60は新技術が多く採用されているため、発売当初はディーラーの整備士も不具合の原因特定や修理に手間取るケースがあったのかもしれません。また、店舗の規模や方針、担当者の経験や知識によっても、対応の質が変わってくる可能性があります。
特に、オーナーが感じるフィーリングの問題(乗り心地の硬さやミッションのギクシャク感など)は、客観的な判断が難しく、ディーラー側が不具合として認識しにくい場合もあります。
しかし、基本的には、CX-60にはマツダのメーカー保証(新車保証)が付帯しています。一般保証は新車登録から3年間または走行距離6万kmまで、エンジンやトランスミッションなどの重要部品に関する特別保証は5年間または走行距離10万kmまでとなっています。この保証期間内に、取扱説明書に従った通常の使用状態で不具合が発生した場合は、原則として無償で修理を受けることができます。
したがって、もしCX-60に何らかの不具合を感じた場合は、まずは諦めずにディーラーに相談し、保証修理の対象となるか確認することが重要です。その際には、いつ、どのような状況で、どんな症状が発生するのかを具体的に伝え、可能であれば動画などで記録しておくと、状況が伝わりやすくなります。
また、前述の通り、CX-60には複数のリコールやサービスキャンペーンが実施されています。これらは、メーカーが設計・製造上の問題や不具合を認め、無償で改善措置を行うものです。対象となる車両や改善内容については、マツダの公式サイトで車台番号を入力すれば確認できますし、対象オーナーには通常、ディーラーから郵送などで通知が届きます。もし通知が来ていない場合でも、該当する可能性があればディーラーに問い合わせてみましょう。
中古車で購入した場合も、リコール未実施であれば無償で対応してもらえます。整備体制については、マツダディーラーであれば、CX-60に関する整備情報や専用の診断機器などが揃っているため、安心して任せることができます。
ただし、ディーラーによっては予約が取りにくかったり、修理に時間がかかったりする場合もあります。もしディーラーの対応に納得がいかない場合は、別のマツダディーラーに相談してみるか、マツダのカスタマーセンターに問い合わせるという方法もあります。いずれにしても、不具合発生時には、保証制度やリコール情報をうまく活用し、粘り強く対応を求めることが大切です。
CX-60 ディーゼルエンジンは本当に「やばい」のか?煤問題や燃費を検証
- 直列6気筒ディーゼルはパワフルな走りと良好な燃費を両立していると評価
- 一部で煤(すす)の堆積によるDPF関連のトラブル懸念の声も
- 実燃費は乗り方で変動。高速中心なら20km/L超えも可能だが、街乗りでは伸び悩む傾向
マツダCX-60の大きな魅力の一つが、新開発された「e-SKYACTIV D」と呼ばれる3.3L直列6気筒ディーゼルエンジンです。このエンジンは、マイルドハイブリッドシステム(M HYBRID BOOST)と組み合わされ、最高出力254ps(S Package除く)、最大トルク550Nmという、このクラスのSUVとしては非常にパワフルなスペックを誇ります。その力強い走りと、ディーゼルならではの経済性(燃費性能)に期待してCX-60を選んだ、あるいは検討している方も多いでしょう。
しかし、一方でディーゼルエンジン特有の問題、特に煤(すす)の堆積によるDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)関連のトラブルを懸念する声や、実際の燃費性能について疑問視する声も聞かれます。果たしてCX-60のディーゼルエンジンは本当に「やばい」のでしょうか?その実力と注意点を検証してみましょう。
まず、走行性能に関して言えば、この直列6気筒ディーゼルエンジンは多くのユーザーから高く評価されています。550Nmという強大なトルクを低回転域から発生させるため、車両重量が1.9トン近くあるCX-60のボディを軽々と加速させます。特に高速道路での合流や追い越し加速は余裕綽々で、非常に快適かつ安定したクルージングが可能です。直列6気筒ならではのスムーズな回転フィールも魅力で、「ディーゼルとは思えないほど静かで滑らか」といった声も聞かれます。マイルドハイブリッドシステムのアシストもあり、発進時などのレスポンスも良好です。
次に、懸念されるDPF関連のトラブルについてです。ディーゼルエンジンは構造上、どうしても煤が発生しやすく、それを除去するためにDPFが装着されています。DPFは、溜まった煤を高温で燃焼させる「再生」という作業を自動で行いますが、短距離走行や低速走行が多い使い方(いわゆるチョイ乗り)を繰り返していると、再生がうまく完了せず、DPFが詰まってしまうことがあります。
DPFが詰まると、警告灯が点灯したり、エンジンの出力が低下したりといった不具合が発生し、最悪の場合は高額なDPF交換が必要になることもあります。CX-60のディーゼルエンジンが、特にDPFトラブルを起こしやすいという報告は現時点では多くありませんが、ディーゼル車である以上、DPFの再生を意識した乗り方(たまには高速道路を走るなど)を心がけるに越したことはありません。マツダもこの点については、取扱説明書などで注意喚起を行っています。
最後に燃費性能です。CX-60ディーゼルモデルのカタログ燃費(WLTCモード)は、グレードによって異なりますが、18.3km/L~19.8km/Lと、このクラスのSUVとしては非常に優秀な数値を達成しています。実際の燃費(実燃費)については、ユーザーの乗り方によって大きく変動しますが、インターネット上の燃費記録サイトなどを見ると、高速道路中心の走行であれば20km/Lを超えるという報告も少なくありません。
一方で、市街地走行がメインになると、10km/L台前半まで落ち込むこともあるようです。特にストップ&ゴーが多い都市部では、期待したほどの燃費が出ない可能性もあります。とはいえ、同クラスのガソリンエンジンSUVと比較すれば、燃料費(軽油はガソリンより安い)を含めたトータルコストで優位性があると言えるでしょう。結論として、CX-60のディーゼルエンジンは、パワフルな走りと優れた燃費性能を高いレベルで両立しており、「やばい」どころか非常に魅力的なエンジンです。
ただし、DPFの問題はディーゼル車の宿命とも言えるため、乗り方には少し気を使う必要があるかもしれません。燃費についても、過度な期待はせず、自分の使い方に合ったものかを見極めることが大切です。
初期型と改良後の違いは?中古車購入時の注意点
- 乗り心地(特にリアサス)と8速ATの制御が主な改良点
- 2023年後半以降のモデルは対策が進んでいる可能性が高い
- 中古車は年式と走行距離、リコール対応履歴、車両状態の確認が必須
これまで見てきたように、マツダCX-60は、特に発売初期のモデルにおいて乗り心地やミッションに関する課題を抱えていました。これらの問題点は、その後の年次改良やソフトウェアアップデートによって改善が図られています。そのため、これからCX-60の中古車を購入しようと考えている方にとっては、「どの年式のモデルを選ぶか」が非常に重要なポイントになります。
初期型と改良後のモデルで具体的にどのような違いがあるのか、そして中古車選びで注意すべき点を解説します。まず、大きな改良点として挙げられるのが「乗り心地」です。前述の通り、初期型モデル(主に2022年9月~2023年夏頃生産)では、リアサスペンションの硬さや突き上げ感が指摘されていました。
これに対し、マツダは2023年秋頃の年次改良(一部改良)で、リアダンパーの特性を変更し、よりしなやかな乗り心地を目指したとされています。したがって、乗り心地を重視するのであれば、2023年後半以降に生産された改良後モデルを選ぶ方が、満足度は高い可能性が高いです。
次に「8速ATの制御」です。低速時のギクシャク感や変速ショックといった問題に対しては、主にソフトウェアアップデートで対応が進められています。これは特定の年次改良というよりは、生産時期やディーラーでのアップデート適用状況によって異なります。改良後のモデルであれば、工場出荷時点である程度改善されたソフトウェアが搭載されていると考えられますが、中古車の場合は、過去にどのようなアップデートが適用されているかを確認することが望ましいです。
ディーラーで整備記録などを確認できれば理想的です。その他、細かな点では、一部装備の見直しやグレード体系の変更などが行われている場合もありますが、乗り心地とミッション制御が、初期型と改良後モデルの最も大きな違いと言えるでしょう。
では、中古車を選ぶ際には具体的に何をチェックすべきでしょうか?まず基本となるのは「年式」と「走行距離」です。上記の改良点を考慮すると、可能であれば2023年後半以降の年式(=改良後モデル)が狙い目となります。走行距離は少ないに越したことはありませんが、極端に少ない場合は、逆に不具合を抱えてあまり乗られなかった可能性もゼロではありません。
年式相応の走行距離(年間1万km程度)で、きちんとメンテナンスされてきた車両が良いでしょう。次に重要なのが「リコール・サービスキャンペーンの対応履歴」です。CX-60は複数のリコールが出ていますので、対象車両かどうか、そして対策済みかどうかを必ず確認しましょう。これは販売店に確認するか、マツダの公式サイトで車台番号を入力して調べることも可能です。もちろん、修復歴(事故歴)の有無も必ずチェックが必要です。
そして、最も重要なのが「車両状態の確認」です。内外装の傷や汚れ、エンジンやミッションの状態(異音、振動、変速ショックなど)、電装品の動作、そして何よりも「試乗」です。
試乗では、乗り心地(特に後席)、低速でのミッションの挙動、ハンドリングなどを重点的にチェックしましょう。可能であれば、信頼できる第三者機関の鑑定書が付いている車両や、保証が充実しているディーラー系の認定中古車を選ぶと、より安心して購入できるでしょう。価格だけで判断せず、車両の状態や改良状況をしっかりと見極めることが、CX-60の中古車選びで後悔しないための鍵となります。
CX-60の魅力とライバル比較:後悔しないための最終チェック
- 「やばい」ほど美しい?CX-60のデザインと高級感あふれる内装を評価
- FRベースの走りは「やばい」?CX-60のハンドリングと走行性能
- CX-5から乗り換えて後悔?CX-60との比較とユーザーの声
- CX-60 中古車購入の注意点!価格相場と狙い目の年式・グレード(重複のため内容変更検討)
- 支払総額はいくら?CX-60の新車・中古車価格と諸費用
- CX-60の燃費は実際どう?ディーゼル/PHEV/ガソリンの実燃費レビュー
- 改良は進んでいる?CX-60の年次改良と今後の期待
「やばい」ほど美しい?CX-60のデザインと高級感あふれる内装を評価
- 魂動デザインを深化させ、FRらしい力強く流麗なプロポーションを実現
- インテリアは上質な素材と日本の美意識を取り入れた高級感のある空間
- 特に上位グレードの内装は、欧州プレミアムSUVに匹敵するとの声も
CX-60に対するネガティブな評判がある一方で、手放しで「やばい(=素晴らしい)」と称賛されることが多いのが、そのエクステリアデザインとインテリアの質感です。
マツダのデザインテーマ「魂動(こどう)-SOUL of MOTION」は、生命感あふれるダイナミックな造形を追求してきましたが、CX-60ではそれをさらに深化させ、新たなステージへと引き上げました。特に、新開発のFRプラットフォームを採用したことで、これまでのマツダ車とは一線を画す、伸びやかで力強いプロポーションを実現しています。
具体的には、エンジンを縦置きにしたことで実現した長いボンネット(ロングノーズ)と、後方に引かれたキャビン(ショートデッキ)が、古典的でありながらもスポーティでエレガントなFR車ならではの佇まいを生み出しています。フロントマスクは、大型のシグネチャーウイングと、それに連続するような薄型のヘッドランプが特徴的で、ワイド感と精悍さを強調しています。
サイドビューは、無駄なラインを削ぎ落とし、光の移ろいによって面の表情が変化する、繊細で美しい造形となっています。この存在感のあるデザインは、街中でも目を引き、「所有する喜び」を感じさせてくれる大きな魅力と言えるでしょう。
インテリアに目を向けると、そこにはエクステリア以上に「やばい」と評価されるほどの高級感とこだわりが詰まっています。水平基調のインパネデザインは、視覚的な広がりと落ち着きを与え、ドライバーが運転に集中できる空間を作り出しています。素材選びにも徹底的にこだわり、グレードに応じて、触感の良いソフトパッド、リアルウッド(楓やバーズアイメイプル)、ナッパレザー、クロームメッキ、そして日本の伝統的な織物や縫製の技法(かけ縫いなど)を取り入れた加飾などが用いられています。
特に「Premium Modern」や「Premium Sports」といった上位グレードの内装は、まるで高級家具のような設えであり、その質感は同価格帯の国産SUVはもちろん、価格が上の欧州プレミアムSUVと比較しても遜色ないレベルにある、と多くのユーザーや評論家から高く評価されています。シートも、体のラインにフィットするように設計されており、見た目の美しさだけでなく、長時間の運転でも疲れにくい快適性を備えています。
もちろん、デザインや質感の好みは人それぞれです。中には「マツダ車はどれも同じに見える」「少し装飾が過剰に感じる」といった意見もあるかもしれません。また、ベースグレードの内装は、上位グレードほどの華やかさはありません。しかし、全体としてCX-60のデザインと内装のクオリティが、マツダの新たなフラッグシップモデルとして、非常に高いレベルにあることは間違いないでしょう。このデザインと内装の美しさに惹かれてCX-60を選ぶ、という人も少なくありません。
ネガティブな評判がある一方で、この圧倒的なデザイン力と高級感が、CX-60が持つ大きな魅力であり、「やばい」と称賛される所以なのです。購入を検討する際は、ぜひ実車を見て、触れて、その質感の高さを確かめてみてください。
FRベースの走りは「やばい」?CX-60のハンドリングと走行性能
- 縦置きFRプラットフォーム採用により、素直で自然なハンドリングを実現
- 直列6気筒エンジンのスムーズな回転フィールと力強いトルクが魅力
- 高速走行時の安定性は高いが、街中での軽快感はボディサイズなり
CX-60が「やばい」と言われるもう一つの側面(こちらは主にポジティブな意味で)が、その「走り」の質感です。マツダは「人馬一体」というキーワードを掲げ、ドライバーの意のままに操れる気持ちの良い走りを目指してきましたが、CX-60ではその理想をさらに追求するために、新開発の縦置きエンジン・FR(後輪駆動)ベースのプラットフォームを採用しました。これは、マツダの量販SUVとしては初の試みであり、走行性能に対する期待は非常に大きいものでした。
実際にCX-60の走りは「やばい」ほど素晴らしいのでしょうか?そのハンドリング性能や走行性能を詳しく見ていきましょう。まず、FRプラットフォームの採用による最大のメリットは、ハンドリングの素直さです。エンジンを縦置きにすることで、前後の重量配分を最適化しやすく、また前輪が操舵に専念できるため、コーナリング時の回頭性が向上します。実際にCX-60を運転してみると、ステアリングを切った際の車の動きが非常に自然で、ドライバーの意図したラインをスムーズにトレースしていく感覚があります。
全長4.7m超、全幅1.89mという大柄なボディを感じさせない、軽快で一体感のあるハンドリングは、まさに「人馬一体」の思想を体現していると言えるでしょう。特にワインディングロードなどでは、その素直な挙動と安定感が際立ち、運転する楽しさを存分に味わうことができます。
この優れたハンドリング性能をさらに引き立てるのが、パワフルなエンジンラインナップです。特に3.3L直列6気筒ディーゼルターボエンジンは、低回転から湧き上がる強大なトルク(550Nm)と、6気筒ならではの非常にスムーズな回転フィールが魅力です。アクセル操作に対するレスポンスも良く、力強い加速と伸びやかなフィーリングを両立しています。PHEV(プラグインハイブリッド)モデルは、システム総合で327ps/500Nmという圧倒的なパワーを発揮し、EV走行による静かで滑らかな走りも可能です。
2.5Lガソリンエンジンモデルは、必要十分なパワーと扱いやすさが特徴です。これらのエンジンと、前述の8速AT(改良が進んだ現在では、ダイレクト感のあるフィーリングが評価される場面も増えています)、そしてFRベースのAWDシステム(i-ACTIV AWD)が組み合わさることで、CX-60は様々な路面状況で安定した力強い走りを提供します。高速道路での直進安定性も非常に高く、長距離クルージングも得意とするところです。
ただし、良い点ばかりではありません。CX-60はそのボディサイズと車両重量(特にディーゼルやPHEVは1.9トン前後)から、街中での取り回しや、狭い駐車場での扱いに気を使う場面があるのは事実です。最小回転半径は5.4mと、サイズを考えれば健闘していますが、絶対的な大きさからくる扱いにくさを感じる可能性はあります。また、乗り心地に関しては、前述の通り初期型では硬さが指摘されており、スポーティなハンドリングとのトレードオフという側面もありました(現在は改良されています)。
総合的に見ると、CX-60の走りは、FRプラットフォームとパワフルなエンジンによって、これまでの国産SUVとは一線を画す、ダイレクトで質感の高いものに仕上がっています。特に、高速道路やワインディングでの安定感と運転する楽しさは、「やばい」と感じる人も多いでしょう。ただし、街乗りでの軽快さや乗り心地の快適性を最優先する場合には、他の選択肢(例えばCX-5など)と比較検討する必要があるかもしれません。試乗を通じて、その走りの個性が自分の好みに合っているかを確認することが重要です。
CX-5から乗り換えて後悔?CX-60との比較とユーザーの声
- CX-60はCX-5よりボディサイズが大きく、価格帯も上になる
- 走行性能や内外装の質感はCX-60が勝るが、乗り心地や扱いやすさではCX-5に分がある部分も
- 自身の使い方や予算に合わせて、どちらが最適か見極めることが重要
マツダSUVの主力モデルとして長年人気を集めてきたCX-5。CX-60が登場したことで、CX-5のオーナーや購入検討者の中には、「CX-60に乗り換えるべきか?」「CX-5とCX-60、どっちが良いの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実際にCX-5からCX-60に乗り換えたユーザーの声や、両車の比較を通じて、後悔しない選択をするためのポイントを探ってみましょう。
まず、基本的な車両コンセプトとポジショニングが異なります。CX-5は、扱いやすいサイズ感と優れたコストパフォーマンス、FF(前輪駆動)ベースながらもマツダらしい走りを楽しめる、バランスの取れたミドルサイズSUVです。一方、CX-60は、より上級志向のラージサイズSUVであり、新開発のFRプラットフォームや直列6気筒エンジンを採用するなど、走行性能や内外装の質感に、より一層こだわって開発されました。当然、価格帯もCX-60の方がCX-5よりも100万円以上高くなります。
では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?まずボディサイズですが、CX-60(全長4740mm、全幅1890mm、全高1685mm ※代表値)は、CX-5(全長4575mm、全幅1845mm、全高1690mm)と比較して、全長で約165mm、全幅で約45mm大きくなっています。この差は、特に市街地での取り回しや駐車のしやすさに影響します。
小回りの利きやすさや運転のしやすさを重視するなら、CX-5の方が有利と言えるでしょう。室内空間については、CX-60の方が全体的にゆとりがありますが、CX-5も大人5人が十分に快適に過ごせるスペースを確保しています。荷室容量も、CX-60の方が若干大きいですが、CX-5も実用上十分な広さを持っています。走行性能に関しては、やはりFRプラットフォームやパワフルなエンジンを持つCX-60に分があります。
高速走行時の安定性や、ワインディングでのハンドリング性能、力強い加速感などは、CX-60が明らかに上回る部分です。ただし、乗り心地については注意が必要です。前述の通り、CX-60(特に初期型)は硬さが指摘されており、路面の凹凸に対する吸収性や快適性という点では、熟成されたCX-5の方が優れていると感じる人も多いようです。(CX-60も改良により改善されています)
内外装の質感についても、CX-60の方がより上質で高級感がありますが、CX-5も年次改良を重ねており、質感は十分に高いレベルにあります。価格差を考えると、CX-5のコストパフォーマンスは依然として非常に高いと言えます。実際にCX-5からCX-60に乗り換えたユーザーの声を見てみると、「走りの質感が格段に上がった」「内装の高級感に満足している」といったポジティブな意見がある一方で、「思ったより乗り心地が硬かった」「サイズが大きくて運転に気を使う」「価格ほどの差を感じられなかった」といった、やや後悔に近いネガティブな意見も見られます。
結局のところ、どちらが良いかは、個々のユーザーが何を重視するかによって異なります。予算に余裕があり、より高い走行性能や内外装の質感を求めるのであればCX-60、扱いやすいサイズ感やコストパフォーマンス、熟成された快適性を重視するならCX-5、という選択になるでしょう。両方の車種をじっくりと比較検討し、試乗して、ご自身のライフスタイルや好みに合った一台を選ぶことが、後悔しないための最も重要なポイントです。
支払総額はいくら?CX-60の新車・中古車価格と諸費用
- 新車価格は約300万円台前半から600万円台半ばまでと幅広い
- グレードやエンジン、オプションによって価格は大きく変動
- 中古車価格もこなれてきているが、諸費用込みの支払総額を確認することが重要
マツダCX-60の購入を検討する上で、最も気になるのがやはり価格でしょう。車両本体価格はもちろんですが、実際に乗り出すまでには、オプション費用や税金、保険料などの諸費用も必要になります。最終的に「支払総額」がいくらになるのかを把握しておかないと、予算オーバーで後悔することにもなりかねません。
ここでは、CX-60の新車・中古車の価格帯と、支払総額の目安について解説します。まず、新車の車両本体価格を見てみましょう。CX-60は、搭載されるエンジン(2.5Lガソリン、3.3Lディーゼル、PHEV)や駆動方式(FR/AWD)、そして装備内容によって非常に多くのグレードが設定されており、価格帯も幅広いです。最も安価なグレードは2.5Lガソリンエンジン搭載の「25S S Package」(FR)で約330万円から、最も高価なグレードはPHEVモデルの「PHEV Premium Modern/Sports」(AWD)で約630万円となっています(2025年4月時点)。人気の中心である3.3Lディーゼルエンジン搭載モデルは、約360万円(XD)から約550万円(XD-HYBRID Premium Modern/Sports)までの価格帯です。このように、どのエンジン、どのグレードを選ぶかによって、価格は大きく変動します。
車両本体価格に加えて、考慮しなければならないのがオプション費用です。ボディカラーによっては追加料金が必要な場合があります(例:ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリックなど)。また、ナビゲーション用SDカード(マツダコネクト本体は標準装備の場合が多い)、ETC車載器、ドライブレコーダー、フロアマット、サンルーフ、各種エアロパーツなど、追加したいオプションによって費用は数十万円単位で変わってきます。特に、Boseサウンドシステムやナッパレザーシートといった魅力的なメーカーオプションは、上位グレードにしか設定されていなかったり、パッケージオプションとして他の装備とセットになっていたりする場合があるので注意が必要です。
さらに、忘れてはならないのが諸費用です。これには、自動車税(種別割)、環境性能割、自動車重量税といった税金、自賠責保険料、リサイクル料金、そして登録や納車に関わる手数料(検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、納車費用など)が含まれます。これらの諸費用は、購入する車両の価格や重量、燃費性能、登録時期、販売店などによって変動しますが、一般的には車両本体価格の10%~15%程度を見込んでおくと良いでしょう。
これらの車両本体価格、オプション費用、諸費用を合計したものが、最終的な「支払総額」となります。例えば、車両本体価格が450万円のディーゼルモデルに、一般的なオプション(ナビSD、ETC、ドラレコ、マット等)と諸費用を加えると、支払総額は500万円を超えるケースが多くなります。中古車の場合は、年式、走行距離、グレード、車両状態によって価格は大きく変動します。発売から時間が経ち、中古車市場にも多くのCX-60が出回るようになってきました。
初期型であれば、新車価格よりもかなり安価(例えば300万円台後半~)で見つけることも可能です。ただし、中古車の場合も、車両本体価格だけでなく、車検の残り期間や整備費用、保証の有無、そして諸費用(名義変更手数料、納車準備費用など)を含めた支払総額を確認することが重要です。カーセンサーやGoo-netといった中古車情報サイトで相場を調べたり、販売店で見積もりを取ったりして、予算内で収まるか、そしてその価格に見合う価値があるかを慎重に判断しましょう。ローンを利用する場合は、金利も含めた総支払額を把握しておく必要があります。
CX-60の燃費は実際どう?ディーゼル/PHEV/ガソリンの実燃費レビュー
- ディーゼルは高速中心なら良好な燃費だが、街乗りではカタログ値との乖離も
- PHEVはEV走行をうまく活用すれば燃費を大幅に抑えられる
- ガソリンモデルは必要十分な性能だが、燃費面ではディーゼルやPHEVに劣る
CX-60を選ぶ上で、パワートレインの選択は重要なポイントです。現在、日本国内では主に3種類のパワートレイン(3.3L直列6気筒ディーゼルターボ、2.5Lプラグインハイブリッド、2.5Lガソリン)が用意されており、それぞれ走行性能だけでなく燃費性能も異なります。特に燃料費や環境性能を気にする方にとっては、カタログ燃費だけでなく、実際の使用状況における「実燃費」がどの程度なのかは非常に気になるところでしょう。
「思ったより燃費が悪くて後悔した…」とならないために、各パワートレインの燃費性能について、ユーザーレビューや燃費記録サイトの情報などを参考に見ていきましょう。まず、最も注目度が高い3.3L直列6気筒ディーゼルエンジン(e-SKYACTIV D)です。カタログ燃費(WLTCモード)は、グレードや駆動方式によって異なりますが、18.3km/L~19.8km/Lと、このクラスのSUVとしてはトップクラスの数値を誇ります。実際の燃費については、乗り方によって大きく変動しますが、高速道路を一定速度で巡航するような場面では、20km/Lを超えるという報告も多く見られます。
これは、低回転からトルクフルなエンジン特性と、8速ATの効率の良さ、そしてマイルドハイブリッドシステムの効果によるものと考えられます。しかし、市街地走行がメインになると、燃費は伸び悩む傾向があります。ストップ&ゴーが多い環境では、10km/L台前半、場合によっては10km/Lを切ることもあるようです。これは、車両重量が重いことや、DPF再生のために燃料を余分に消費する場面があることなどが影響していると考えられます。
次に、2.5Lプラグインハイブリッド(e-SKYACTIV PHEV)です。カタログ燃費(WLTCモード・ハイブリッド燃料消費率)は14.6km/Lですが、PHEVの燃費を語る上で重要なのは、EV走行(電気のみでの走行)の活用度です。CX-60 PHEVは、満充電状態から約70km以上のEV走行が可能とされています。自宅などで充電できる環境があり、日常的な移動距離がEV走行可能距離内であれば、ガソリンをほとんど使わずに走行できるため、実質的な燃費は非常に良くなります。
ただし、充電環境がない場合や、長距離移動でバッテリー残量がなくなると、エンジン主体のハイブリッド走行となり、その場合の燃費はディーゼルモデルに劣る可能性があります。車両価格が高い点も考慮に入れる必要があります。最後に、2.5Lガソリンエンジン(SKYACTIV-G 2.5)です。カタログ燃費(WLTCモード)は13.1km/L前後と、ディーゼルやPHEVと比較すると見劣りします。実燃費についても、市街地走行では1桁台、高速走行でも10km/L台前半という報告が多く、燃費性能を重視するユーザーには物足りないかもしれません。ただし、車両価格が最も安価であり、エンジン自体のフィーリングが自然で扱いやすいというメリットもあります。
このように、CX-60の燃費性能は、選択するパワートレインとユーザーの乗り方(走行環境、充電環境の有無など)によって大きく異なります。単純なカタログ燃費だけでなく、ご自身の使い方を想定し、燃料費(軽油、ガソリン、電気代)や車両価格、税金の優遇措置などをトータルで考慮して、どのパワートレインが最も適しているかを見極めることが重要です。特にディーゼルモデルは、高速長距離移動が多いユーザーにとっては非常に経済的ですが、街乗り中心の方にとっては期待ほどのメリットが得られない可能性もあります。試乗の際には、燃費計の表示なども参考にしてみると良いでしょう。
改良は進んでいる?CX-60の年次改良と今後の期待
- 発売後、乗り心地やミッション制御を中心に年次改良が実施されている
- ソフトウェアアップデートも随時行われ、初期モデルの改善も図られている
- 今後もさらなる熟成や、新たな機能・装備の追加が期待される
CX-60は、マツダの新世代ラージ商品群の先駆けとして、多くの新技術を投入して市場に登場しました。それゆえに、発売初期には乗り心地やミッション制御などで課題も露呈しましたが、マツダはその後、着実に改良を進めています。「初期型はちょっと…」と感じていた方も、現在のCX-60がどのように進化しているのか、そして今後どのような改良が期待できるのかは気になるところでしょう。
ここでは、CX-60の年次改良の状況と、今後の期待について見ていきます。まず、これまでに行われた主な改良点としては、やはり「乗り心地の改善」と「8速ATの制御の最適化」が挙げられます。乗り心地に関しては、2023年秋頃の一部改良で、主にリアサスペンションのダンパー特性が見直されました。これにより、初期型で指摘されていた突き上げ感が緩和され、よりしなやかで快適な乗り心地になったと評価されています。8速ATの制御についても、ソフトウェアアップデートが複数回実施されており、低速域でのギクシャク感や変速ショックが大幅に低減されています。
これらの改良は、新車として生産されるモデルだけでなく、既存のオーナーに対しても、ディーラーでのアップデートという形で提供される場合が多く、初期型モデルの改善も進められています。
乗り心地やミッション制御といった、発売当初の主な課題に対する改良が進んだことで、CX-60の商品力は着実に向上していると言えます。これらは、ユーザーからのフィードバックや市場の評価を真摯に受け止め、迅速に対応するマツダの姿勢の表れとも言えるでしょう。また、ソフトウェアアップデートは今後も継続的に行われる可能性があり、さらなる制御の最適化や、場合によっては新しい機能の追加なども期待できるかもしれません。
例えば、インフォテインメントシステムであるマツダコネクトの機能向上や、運転支援システム「アイアクティブセンス」の性能向上などが考えられます。特に、OTA(Over-the-Air)によるソフトウェアアップデート機能が今後強化されれば、ディーラーに足を運ばなくても、常に最新の状態に保つことが可能になるかもしれません。
装備面では、年次改良ごとに、新しいボディカラーの追加や、一部グレードでの標準装備の見直し、オプション設定の変更などが行われるのが一般的です。ユーザーからの要望が高い装備、例えば、より快適性を高める機能や、利便性を向上させるアイテムなどが、今後の改良で追加される可能性もあります。
また、マツダは定期的に特別仕様車を発売することでも知られています。CX-60においても、質感や個性をさらに高めた魅力的な特別仕様車が登場することが期待されます。CX-60は、マツダにとって非常に重要な戦略モデルであり、今後も継続的な改良によって、その完成度を高めていくと考えられます。
特に、初期のネガティブな評判を払拭し、プレミアムSUVとしての地位を確固たるものにするためには、さらなる熟成が不可欠です。これからCX-60の購入を検討する方は、最新の改良状況や今後のモデルチェンジ情報なども注視していくと良いでしょう。現在のモデルでも十分に魅力的ですが、さらなる進化にも期待が持てる一台と言えます。
まとめ:CX-60の「やばい」評価を理解し後悔しない選択を
- CX-60は「やばい」と称賛される魅力(デザイン、内装、走り)と、「やばい」と批判される課題(乗り心地、ミッション、不具合)を併せ持つ
- 特に初期型モデル(2022年後半~2023年前半)には課題が多かったが、年次改良やアップデートで改善が進んでいる
- 乗り心地やミッションのフィーリングは個人の感覚差が大きいため、必ず試乗して確認することが重要
- ディーゼル、PHEV、ガソリンといったパワートレインの特性と、自身の使い方(走行距離、充電環境など)を照らし合わせて選ぶ
- CX-5など、他の車種との比較も行い、サイズ感、価格、性能のバランスを見極める
- 中古車を検討する場合は、年式(改良後か)、走行距離、リコール対応履歴、車両状態を入念にチェックする
- ディーラーの対応やメーカー保証、リコール制度を理解し、活用する
- インターネット上のクチコミは参考程度とし、最終的には自身の判断で納得できる一台を選ぶ
- 「やばい」評判の背景を理解した上で、それでも魅力を感じるなら、CX-60は満足度の高い選択肢になり得る
- 今後のさらなる改良や熟成にも期待が持てるモデルである
こんにちは!車の情報をお届けする運営者です。CX-60に関するこの記事、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
「CX-60 やばい」というキーワード、インパクトありますよね。私も初めて聞いたときは、良い意味なのか悪い意味なのか、すごく気になりました。調べてみると、本当に賛否両論、良くも悪くも「やばい」クルマなんだな、というのが正直な感想です。
デザインや内装の質感、そしてFRベースの走りは、本当に「やばい」くらい魅力的。特に直列6気筒ディーゼルの力強さとスムーズさは、一度味わうと虜になるかもしれません。まるで「和製プレミアムスポーツSUV」と呼びたくなるような、独特のオーラがあります。
でもその一方で、特にデビュー当初は、乗り心地の硬さやミッションのギクシャク感といった「やばい」課題があったのも事実。せっかく高いお金を出して買ったのに…と、後悔されたオーナーさんがいたのも想像に難くありません。まるで、才能はあるけどちょっと扱いにくい、個性的なアーティストのような印象でしょうか。
幸いなことに、マツダもユーザーの声に耳を傾け、着実に改良を進めています。乗り心地もミッションも、かなり改善されてきているようです。だからこそ、これからCX-60を選ぶなら、できるだけ新しい年式のモデルを試乗して、ご自身の感覚で確かめていただくのが一番だと思います。
どのパワートレインを選ぶか、どのグレードにするか、そしてCX-5など他の選択肢と比較してどうなのか…。悩むポイントはたくさんありますが、この記事が、あなたの後悔しないクルマ選びの一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
ぜひ、あなたにとって最高の「やばい」一台を見つけてくださいね!応援しています!